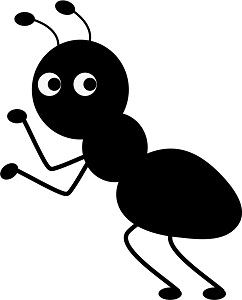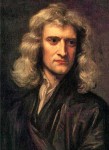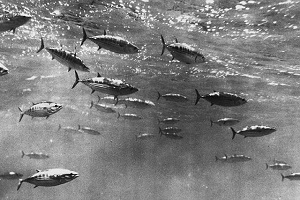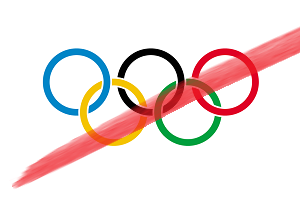- ・ ダンクシュートの「ダンク」とはどういう意味?
- ・ 「付き合うって何?」を超まともなうっとしい解説をする
- ・ 羽目を外すの意味と語源とは?
- ・ 茶碗なのになぜご飯を入れる?その理由とは
- ・ サービスエリアが50キロおきに設置されている理由
- ・ 静かな場所でも安心!最も効果的なくしゃみの対処法
- ・ 髪どめの「カチューシャ」とは日本独自の呼び方だった!?
- ・ 懐石料理と会席料理の違いとは
- ・ 大昔のマグロは捨てられていた?!その理由
- ・ お寺が日本一多い都道府県はどこ?
- ・ イルカがジャンプするのはなぜ?
- ・ オーケストラの音合わせに「オーボエ」が使われる理由
- ・ 水族館でスルメイカを見かけない理由
- ・ 自分自身をくすぐっても笑わない理由
かぼちゃの名前の由来とは?
最終更新日:2020/10/21
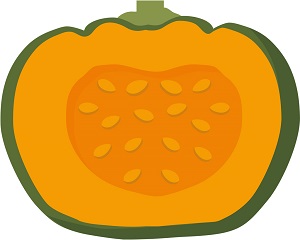
「かぼちゃ」
日本では、ごく当たり前に言われているこの名前ですが、
かぼちゃの名前の由来は、何なのでしょうか?
名前の由来

ポルトガル船が持ってきた瓜がカンボジア産だったから。
日本にかぼちゃが伝わったのは、1500年頃です。
ポルトガル船が日本へやってきて、その船に積まれていた瓜が「かぼちゃ」でした。
そのかぼちゃが「カンボジア」から持ってきたものだったので
「カンボジア」が訛って「かぼちゃ」に変化して定着したとされています。
かぼちゃの漢字に「南」がつくのは?

南蛮渡来を意味している。
かぼちゃは、ウリ科の野菜で、漢字は「南瓜」と書きます。
この漢字に南という字が付くのは、南蛮渡来を意味しており、
南方の野蛮人の略語が「南蛮」で、東南アジア地方を指す言葉でした。
ポルトガル船は、東南アジアを迂回して日本へ来るため「南蛮渡来」という言葉が生まれ
「南蛮渡来でやってきた瓜」という事で、南瓜がかぼちゃとなったのです。
かぼちゃとパンプキン

日本のかぼちゃは英語で「カボチャ・スクワッシュ」などと呼ぶ。
日本でよく食べるかぼちゃは正確には「パンプキン」ではなく、
「カボチャ・スクワッシュ」「ジャパニーズ・スクワッシュ」などと海外では呼ばれています。
「スクワッシュ」は「押しつぶす、ぐちゃぐちゃな」という意味の言葉。
かぼちゃのしわしわな外観から、これをあてはめたのでしょう。
また、海外でのオレンジ色をしたかぼちゃを「パンプキン」とは呼びます。
かぼちゃの呼び方は他にもあるので、詳しくはこちらを見てください。
⇒「かぼちゃ=パンプキン」ではない!?その違いとは
南京、ボウブラ、唐茄子の由来
伝来元や言葉から付けられている。
かぼちゃの名前には他にも「南京、ボウブラ、唐茄子(トウナス)」とありますが
「南京」とは中国の港の南京から来たかぼちゃで、「唐茄子」も中国(唐)から来たことから由来しており、
「ボウブラ」はウリ科の植物を意味するポルトガル語の「abobora」からきています。
~
パンプキンと言えばハロウィンですが、なぜハロウィンでお菓子を配るのか知っていますか?
・なぜハロウィンでお菓子を配るのか?その理由
--
以上、かぼちゃの名前の由来とは?でした。
--