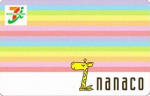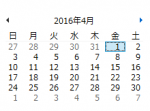- ・ 東京タワーには戦車の鉄が含まれている!?
- ・ 熱中症対策に効果的な食べ物とは?
- ・ ボウリングのピンは元々10本ではなかった
- ・ 冷蔵庫のコンセントが高い位置にある理由
- ・ 春は桜前線、夏はホタル前線というものがある!?
- ・ 海外のダイソーの値段は100円じゃない
- ・ ケガをした手で触ってはいけない!?アマガエルの皮膚の秘密
- ・ 青い車は事故が多い!?その理由とは?逆に少ない色は?
- ・ 人間以外に指紋を持っている動物は居るのか?
- ・ ごたくの意味と語源とは
- ・ どこを回ることなのか?「急がば回れ」の意味や由来とは
- ・ 泥棒に風呂敷を使って盗むイメージがついている理由
- ・ 飛行機の機内で起きた犯罪はどこの国の法律になるのか?
- ・ たかをくくるの意味と語源とは
めどがつくの意味と語源とは
最終更新日:2020/10/21

「めどがついた」
このような言葉を聞いたことあると思います。
では、「めどがつく」とはどういう意味なのでしょうか?
めどがつくの意味とは?

目標や予定などの見通しがつくことを意味している。
「予定のめどが付いた」や「仕事の終了時間のめどが付いた」などの言葉で使われています。
「めど」は漢字で「目途」または「目処」と書きますが、これはあとから当てられた当て字です。
めどがつくの語源とは?

画像引用元:wikipedia「筮竹」
易者(えきしゃ)の道具の蓍(めどぎ)から生まれた言葉。
易者というのは占い師のことです。
易者が使っている道具に、筮竹と呼ばれる細長い竹の棒を使って占いますが
昔は竹ではなく、蓍や蓍萩(めどはぎ)と呼ばれる植物の茎から作った棒を使っていました。
未来を占うことから「めどぎ」「めどはぎ」から生まれた「めど」が「目標」や「目指すところ」という意味になり、
「つく」は「見通しがつく」や「けりがつく」などの「つく」のことを指します。
なので、「目標に見通しがつく」などの言葉が「めどがつく」として呼ばれるようになったようです。
~
また「お開き」と言う言葉がありますが、この「お開き」の語源が何か知っていますか?
・お開きの意味と語源とは
--
以上、めどがつくの意味と語源とはでした。
他の言葉・漢字の雑学
他の雑学(ランダム表示)
--