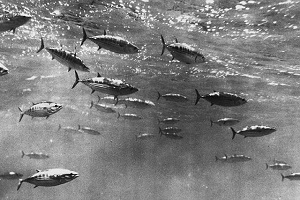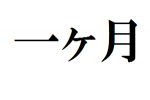- ・ 料理酒の役割・効果。そして使い方。
- ・ 唐辛子はどの部分が一番辛い?
- ・ 青い車は事故が多い!?その理由とは?逆に少ない色は?
- ・ 卵の鮮度を長持ちさせるとっても簡単な方法
- ・ トライアスロンが誕生した理由とは
- ・ 野球の三振はなぜ「K」なのか?意味と理由は?
- ・ 野良猫が母猫かどうかを見分ける方法
- ・ 最も長い英単語は何文字?
- ・ ひもじいの言葉の意味と語源とは
- ・ しっぺ返しの意味と語源とは
- ・ コリー犬は迷子になりやすい!?その理由
- ・ 「かぼちゃ=パンプキン」ではない!?その違いとは
- ・ 揚げ足を取るの意味と語源とは
- ・ つむじを押すと本当に下痢になるのか?そもそも何のツボ?
灯台は関係ない!?「灯台下暗し」の意味や語源とは?
最終更新日:2020/10/21

「灯台下暗し」
このような言葉があると思いますが、灯台と聞くと
港や岬にある灯台を思い浮かべると思いますが、実はその灯台ではないのです。
そもそも灯台下暗しとは
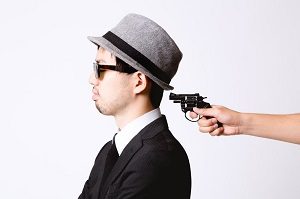
「人は身近な事にはかえって気が付かない」という例え。
自分の身の回りで起きていることは、意外にも分かりにくくなかなか気が付かないものだという
例えですが、灯台も遠くを照らして、足元は真っ暗なので意味合い的には合っていますが、語源は違います。
灯台下暗しの語源

「灯明台(とうみょうだい)」のことを指している。
ここで言う「灯台」とは、大昔で日常的に室内を明るくするために使われていた
「灯明台」または「燭台」のことを指しており、明るく照らされたろうそくの火などの火が
下の方は暗いことから、そのように例えられたとされています。
このことわざは、江戸時代から使われていたようです。
ちなみに

画像引用元:wikipedia「観音崎灯台」
日本で最初の灯台は「観音崎灯台(かんのんざき)」と呼ばれる灯台。
日本で最古の洋式灯台は、神奈川県横須賀市にある「観音崎灯台」です。
この灯台が完成したのは1869年なので、ことわざの灯台とは無関係というのが分かります。
~
ことわざと言えば、「情けは人のためにならず」という言葉がありますが、意味は知っていますか?
・「情けは人の為ならず」は自分のため!?その本当の意味とは
--
以上、灯台は関係ない!?「灯台下暗し」の意味や語源とは?でした。
他の言葉・漢字の雑学
他の雑学(ランダム表示)
--