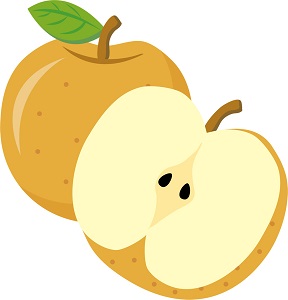- ・ 大文字焼きはなぜ「大」の字なのか?
- ・ 夏休みはなぜ長い?その理由と由来
- ・ 鹿児島県の桜島はなぜ「島」なのか?その理由とは
- ・ なぜ鮭(サケ)の鼻が曲がっている?
- ・ シャンメリーはなぜクリスマスの定番になったのか?
- ・ 犬の鼻が濡れている理由とは?乾くのはどういう時?
- ・ オリンピックで4位以下は何が貰えるのか?
- ・ 画家ゴッホの絵は生前何枚売れたのか?
- ・ 最大のお得技!QUOカード技で最強の還元率を得よう!
- ・ “手当て”の由来・語源とは? ~手に隠された力とは?~
- ・ シンクロの雑学!髪の毛のセット方法は?なぜ大食い?歴史は?
- ・ 砂糖を食べないアリが身近にいるので注意
- ・ 見ると美しい「オーロラ」の正体とは?
- ・ 日本の森林の割合は世界と比べてどのくらい?また一番多い都道府県とは
手塩にかけるの「手塩」とは何のこと?
最終更新日:2020/10/21

「手塩にかけた弟子」「手塩にかけた部下」など
自ら面倒を見て育てることを意味する言葉なのだが
この「手塩」とはいったい何のことなのだろうか。
「手塩」の語が見られるようになった室町時代

※wikipedia「塩」より引用
昔、食事をするときはそれぞれ自分のお膳で食べていたのですが
そのお膳には塩が添えられていました。
この塩を各自好みに応じて食べ物に加えていたそうです。
この塩の膳は元々不浄を払うために使うものでした。
その塩の名称を「手塩」と言いました。
手塩は他人ではなく自分でかけるもの。
「自らの手でかけることで加減を調節する」ことから
「自ら世話をする」という意味を持ち「手塩にかける」という言い方ができたとされています。
「手塩にかける」という言葉が使われ始めたのは江戸時代ごろからとされています。
--
以上、手塩にかけるの「手塩」とは何のこと?でした。
他の言葉・漢字の雑学
他の雑学(ランダム表示)
--