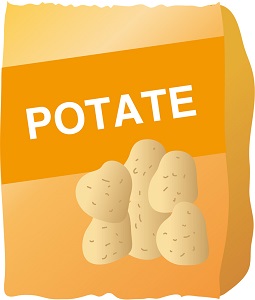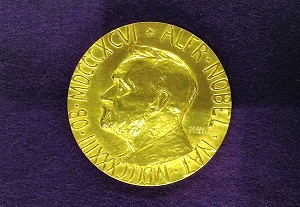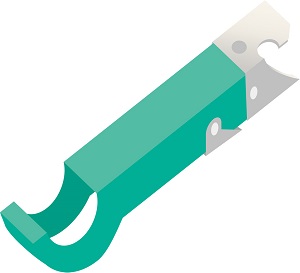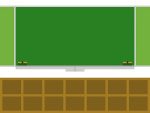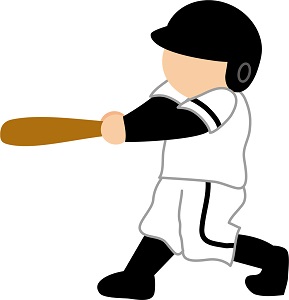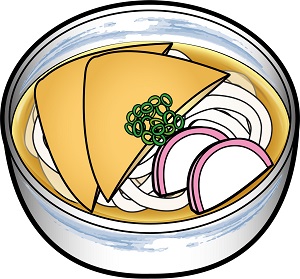- ・ くだらないの意味と語源とは
- ・ なぜメールだと感情的になりやすい?その理由と対策
- ・ かぼちゃの名前の由来とは?
- ・ 空港の一般ラウンジが同伴者も無料になるカードとは?
- ・ ガチンコ勝負の「ガチンコ」の語源とは
- ・ めっぽうの意味と語源とは
- ・ 暗殺「アサシン」の名前の由来とは
- ・ なぜギャンブルにのめり込んでしまうのか?その心理的理由とは
- ・ 深海魚はなぜ水圧に潰れないのか?という考え方が間違っている理由
- ・ なぜ車の中で読書をすると酔うのか?酔わない対策とは?
- ・ キウイフルーツの正しい食べ方は皮ごと食べる!?
- ・ 猫舌なのは猫だけではない。猫舌の由来とは?
- ・ なぜ焼売(シュウマイ)にグリーンピースが乗っているのか?
- ・ はなむけの意味と語源とは
ファスナーは最初は意外な用途だった?~歴史と由来~
最終更新日:2020/10/21

ファスナーって凄い発明だが当初は・・・
どんなに凄いものでも、最初はなかなか受け入れられないものです。
いったいどんな用途で発明され、苦労したのか?
そんなファスナーの歴史を紹介。
最初は靴

※引用元:https://www.ykk.co.jp/japanese/ykk/mame/fas_01.html
ファスナーは靴紐に代わるものとして発明されました。
1891年、アメリカのホイットコム・ジャドソン氏が発明。
自信満々でシカゴ万国博に出展し、目を付けた人が出現。
さっそく会社を設立。ここまでは良かった。
その後、米国郵政公社から郵便袋として採用されるのだが、
「すぐに壊れる」ということで、不評にて終了。
こうして初代ファスナーは終わったのだった。
改良への道と進む。
財布に採用

改良を重ね、財布に利用することで成功を収める。
それからはアメリカ空軍の服にも採用されたりと、
ファスナーは一躍有名になっていきました。
ライバル登場
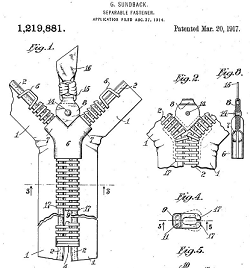
別のメーカーが「ジッパー」として売り出しました。
これが売れたのか、アメリカではファスナーよりもジッパーが有名に。
すっかり「ジッパー」が正式名称のようになりました。
日本では「チャック」とも呼ばれていますが、
これも日本のメーカーによる商品名(チャック印として売られた)です。
--
という感じで、やはり便利なものは認められるものです。
「壊れやすい」というのは今も変わりありませんが、
特に最初は壊れやすかったのでしょう。改良の苦労が目に浮かびます。
ちなみに、ファスナーといえば「社会の窓」。
なぜそう呼ぶようになったのか?知っておきたい。
なぜズボンの前開きを「社会の窓」と呼ぶ?その由来とは
以上、「ファスナーは最初は意外な用途だった?~歴史と由来~」でした。
--