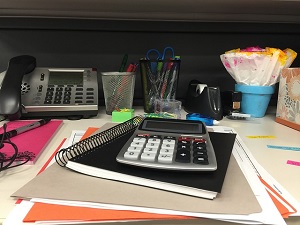- ・ 麦茶パックの保存期間と保存方法
- ・ ジャガイモの名前の由来とは
- ・ 塩梅(あんばい)の意味と語源とは
- ・ パセリの保存期間と保存方法
- ・ 左利きのことをサウスポーと呼ぶ由来・語源
- ・ モンドセレクション受賞=美味いなのか?
- ・ 高速道路にいた人をはねた時の運転手の過失の割合
- ・ 飛行機の燃料はガソリンではなく灯油!?その理由とは?
- ・ 食事をすると仲良くなれる理由は?
- ・ 武士の給料はなぜ米だったのか?その理由
- ・ なぜ「3人で写真を撮ると真ん中の人は早死にする」と言われているのか?
- ・ ひもじいの言葉の意味と語源とは
- ・ 透明な業務用の氷の作り方
- ・ 自分自身をくすぐっても笑わない理由
めどがつくの意味と語源とは
最終更新日:2020/10/21

「めどがついた」
このような言葉を聞いたことあると思います。
では、「めどがつく」とはどういう意味なのでしょうか?
めどがつくの意味とは?

目標や予定などの見通しがつくことを意味している。
「予定のめどが付いた」や「仕事の終了時間のめどが付いた」などの言葉で使われています。
「めど」は漢字で「目途」または「目処」と書きますが、これはあとから当てられた当て字です。
めどがつくの語源とは?

画像引用元:wikipedia「筮竹」
易者(えきしゃ)の道具の蓍(めどぎ)から生まれた言葉。
易者というのは占い師のことです。
易者が使っている道具に、筮竹と呼ばれる細長い竹の棒を使って占いますが
昔は竹ではなく、蓍や蓍萩(めどはぎ)と呼ばれる植物の茎から作った棒を使っていました。
未来を占うことから「めどぎ」「めどはぎ」から生まれた「めど」が「目標」や「目指すところ」という意味になり、
「つく」は「見通しがつく」や「けりがつく」などの「つく」のことを指します。
なので、「目標に見通しがつく」などの言葉が「めどがつく」として呼ばれるようになったようです。
~
また「お開き」と言う言葉がありますが、この「お開き」の語源が何か知っていますか?
・お開きの意味と語源とは
--
以上、めどがつくの意味と語源とはでした。
他の言葉・漢字の雑学
他の雑学(ランダム表示)
--