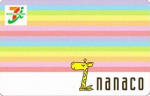- ・ 焦げた物を食べてもがんの原因にはならない?!その理由とは
- ・ 楽天カードは2016年もなぜ人気なのか?
- ・ 金魚に塩水が必要?その理由とは
- ・ 白髪は抜くと本当に増えるのか?逆に禿げる?
- ・ アメンボは何を食べる?食べ物と食べ方を知ろう
- ・ 飼い猫のオスとメスを顔で見分けるのが不可能な理由
- ・ 銀行のトップはなぜ「頭取」なのか?
- ・ アイシャドーの元々の目的とは?
- ・ インターネットが生まれた理由とは
- ・ トランプに隠された枚数やマークの意味
- ・ ゴミ収集車1台の値段っていくら?
- ・ 胡散臭いの意味と語源とは
- ・ 電線にとまっている鳥が感電しないのはなぜ?その理由
- ・ パセリの保存期間と保存方法
てるてる坊主はもともと「娘」のことだった
最終更新日:2020/10/21

天気が晴れになるように、てるてる坊主を吊るす風習がありますが
もともとは「坊主」ではなく、「娘」だったのです。
てるてる坊主の起源とは?

中国の「掃晴娘(そうせいじょう)」から来ている。
てるてる坊主をつるす風習は平安時代に中国から伝わりました。
中国では「掃晴娘」と呼ばれる箒(ほうき)を持った女の子の紙人形のことで
これを吊るすことで晴れになるように祈ったとされています。
なぜ「坊主」になったのか?

日本で雨が止むのを祈るのは修験者(しゅげんしゃ)や旅の僧などの「聖(ひじり)」が多かったから。
日本では、雨が止むことを祈ったのは修験者や旅の僧など「聖」が多かったことから
女の子ではなく、僧侶の姿を模した坊主姿の人形になったのです。
雨を望むてるてる坊主
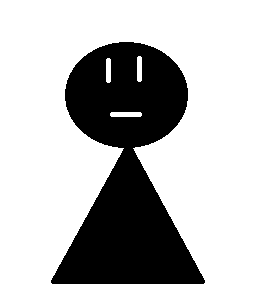
西日本地方では雨を望む黒いてるてる坊主を吊るす風習がある。
「てるてる坊主を逆さにつるすと雨が降る」というのは聞いたことあると思います。
西日本地方では、雨を望む「雨乞い(あまごい)」に黒い坊主姿の人形を吊るす風習が一部であるようです。
--
以上、てるてる坊主はもともと「娘」のことだったでした。
他の物の雑学
他の雑学(ランダム表示)
--