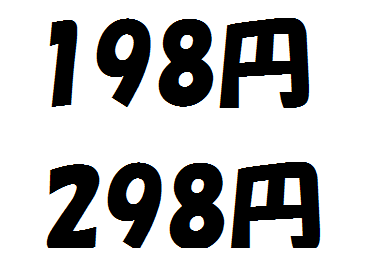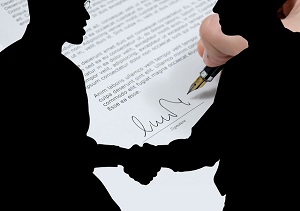- ・ なぜ赤じゃない?血管が青く見える理由とは
- ・ くだを巻くの意味と語源とは
- ・ ホタルの光には方言がある!?発光時間が違った!
- ・ 幽霊に足がないイメージが強い理由とは
- ・ 茶柱が立つとなぜ縁起が良いのか?その理由
- ・ 牡蠣(カキ)がホタテの貝殻で養殖される理由とは?
- ・ トイレットペーパーの幅はなぜ114ミリなのか?
- ・ 宇宙飛行士を襲う「宇宙酔い」とは?
- ・ 永久歯ではなく乳歯が先に生えてくる理由・役割とは?
- ・ あみだくじの由来とは
- ・ 自販機のボタンを同時に複数押したらどのボタンを押したことになる?
- ・ 書く必要がない!?紙幣に製造年が書いていない理由とは
- ・ なぜ雷が鳴ったらへそを隠すのか?その理由
- ・ ビーフストロガノフは牛肉料理ではない!?その名前の由来と理由
間食のことを「おやつ」と呼ぶ理由
最終更新日:2020/10/21

昼食と夕食の間に食べる間食のことを「おやつ」と呼ばれており、
また、「おやつ」と言えば間食として食べられるお菓子のことを意味します。
では、間食のことを「おやつ」と呼ぶのはなぜでしょうか?
おやつとは

おやつは昔の時刻の呼び方からきている。
おやつの「やつ」とは「八つ」で昔の時刻の呼び方からきています。
江戸時代では昼夜を6等分しており、一日を12刻で表しています。
そして、今の午後2時から4時までを「八つ(八つどき)」と呼び、その間に間食をすることから
「おやつ」と呼ぶようになったのです。
おやつの「お」

おやつの「お」は尊敬の接頭語としてつけられている。
おやつの「お」は京都・大阪では本願寺が太鼓を打って「八つ」の時刻を知らせたので
尊敬の接頭語の「お」をつけて「おやつ」と呼ばれるようになったとも言われています。
明治時代

明治時代になってからは「お三時」とも言われている。
明治時代になると時の表示方法が変わり一時、二時と表すようになったので
午後三時ごろにおやつを食べることからおやつのことを「お三時」とも呼ばれていました。
--
以上、間食のことを「おやつ」と呼ぶ理由でした。
他の言葉・漢字の雑学
他の雑学(ランダム表示)
--