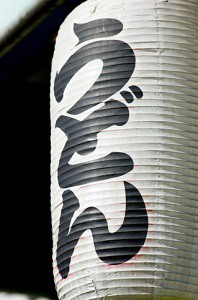- ・
Warning: Trying to access array offset on false in /home/parudou/zatugakuunun.com/public_html/wp-content/themes/wptema/single.php on line 27
Warning: Trying to access array offset on null in /home/parudou/zatugakuunun.com/public_html/wp-content/themes/wptema/single.php on line 27
- ・
Warning: Trying to access array offset on false in /home/parudou/zatugakuunun.com/public_html/wp-content/themes/wptema/single.php on line 27
Warning: Trying to access array offset on null in /home/parudou/zatugakuunun.com/public_html/wp-content/themes/wptema/single.php on line 27
- ・
Warning: Trying to access array offset on false in /home/parudou/zatugakuunun.com/public_html/wp-content/themes/wptema/single.php on line 27
Warning: Trying to access array offset on null in /home/parudou/zatugakuunun.com/public_html/wp-content/themes/wptema/single.php on line 27
- ・
Warning: Trying to access array offset on false in /home/parudou/zatugakuunun.com/public_html/wp-content/themes/wptema/single.php on line 27
Warning: Trying to access array offset on null in /home/parudou/zatugakuunun.com/public_html/wp-content/themes/wptema/single.php on line 27
- ・
Warning: Trying to access array offset on false in /home/parudou/zatugakuunun.com/public_html/wp-content/themes/wptema/single.php on line 27
Warning: Trying to access array offset on null in /home/parudou/zatugakuunun.com/public_html/wp-content/themes/wptema/single.php on line 27
- ・
Warning: Trying to access array offset on false in /home/parudou/zatugakuunun.com/public_html/wp-content/themes/wptema/single.php on line 27
Warning: Trying to access array offset on null in /home/parudou/zatugakuunun.com/public_html/wp-content/themes/wptema/single.php on line 27
- ・
Warning: Trying to access array offset on false in /home/parudou/zatugakuunun.com/public_html/wp-content/themes/wptema/single.php on line 27
Warning: Trying to access array offset on null in /home/parudou/zatugakuunun.com/public_html/wp-content/themes/wptema/single.php on line 27
- ・
Warning: Trying to access array offset on false in /home/parudou/zatugakuunun.com/public_html/wp-content/themes/wptema/single.php on line 42
Warning: Trying to access array offset on null in /home/parudou/zatugakuunun.com/public_html/wp-content/themes/wptema/single.php on line 42
- ・
Warning: Trying to access array offset on false in /home/parudou/zatugakuunun.com/public_html/wp-content/themes/wptema/single.php on line 42
Warning: Trying to access array offset on null in /home/parudou/zatugakuunun.com/public_html/wp-content/themes/wptema/single.php on line 42
- ・
Warning: Trying to access array offset on false in /home/parudou/zatugakuunun.com/public_html/wp-content/themes/wptema/single.php on line 42
Warning: Trying to access array offset on null in /home/parudou/zatugakuunun.com/public_html/wp-content/themes/wptema/single.php on line 42
- ・
Warning: Trying to access array offset on false in /home/parudou/zatugakuunun.com/public_html/wp-content/themes/wptema/single.php on line 42
Warning: Trying to access array offset on null in /home/parudou/zatugakuunun.com/public_html/wp-content/themes/wptema/single.php on line 42
- ・
Warning: Trying to access array offset on false in /home/parudou/zatugakuunun.com/public_html/wp-content/themes/wptema/single.php on line 42
Warning: Trying to access array offset on null in /home/parudou/zatugakuunun.com/public_html/wp-content/themes/wptema/single.php on line 42
- ・
Warning: Trying to access array offset on false in /home/parudou/zatugakuunun.com/public_html/wp-content/themes/wptema/single.php on line 42
Warning: Trying to access array offset on null in /home/parudou/zatugakuunun.com/public_html/wp-content/themes/wptema/single.php on line 42
- ・
Warning: Trying to access array offset on false in /home/parudou/zatugakuunun.com/public_html/wp-content/themes/wptema/single.php on line 42
Warning: Trying to access array offset on null in /home/parudou/zatugakuunun.com/public_html/wp-content/themes/wptema/single.php on line 42
うどんはいつから食べられるようになった?その歴史
最終更新日:2020/10/21

うどんとは小麦粉を練り、長く切ったある程度の太さと幅を持つ麺を茹でて
つゆに浸し食べたりすることを言います。
私たちは普段から食べておりよく知っているうどん。
ではうどんはいつから食べられるようになったのか。
うどんの歴史
ごく一般的によく知られているうどんですが
実はうどんの誕生は諸説あり定かになっていません。
うどんは奈良・平安時代に中国から伝わり、平安時代には「麦縄(むぎなわ)」と呼ばれる
うどんの起源とも呼ばれる麺が誕生した。この頃はまだ米と小麦粉を混ぜて作られていた。
そして小麦粉で作る素麺である小麦粉を練り薄くのばしたものを「切り麦」と呼ぶものができた。
この切り麦が現在食べられている麺の誕生である。
そして本格的にうどんが食べられるようになったのは江戸時代で
その頃には天ぷらや鴨南蛮などの具をのせたうどんも登場していた。
つまりこの説をまとめると
うどん起源は奈良・平安時代頃からあるが、現在のうどんが本格的に食べられるようになったのは江戸時代
と言う事になる。
食欲のない時はうどんが良い
うどんはとても消化の良い食品です。体調を崩した時や風邪をひいてしまった際は
うどんを食べると体調がよくなると言われています。
以上うどんはいつから食べられるようになった?その歴史でした。
他の食べ物の雑学
他の雑学(ランダム表示)
--