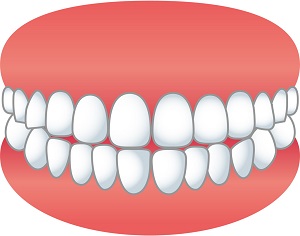- ・ 得体の知れないの意味と語源とは
- ・ 雨が降りそうな雲はなぜ黒い?雨雲が黒い理由とは?
- ・ 猫舌なのは猫だけではない。猫舌の由来とは?
- ・ 判子の側面にある凹んだ部分の名前とは
- ・ イオンで買い物する人が持っていないと情弱となるカードとは?
- ・ 相撲の土俵が丸い理由とは
- ・ 鎌倉や奈良などの大仏の大きさには基準はあるのか?
- ・ 孫の手は「孫」の手ではなかった?!
- ・ 高知の名物のカツオのタタキの誕生秘話とは
- ・ カレーに福神漬けがあるのはなぜ?その歴史を知ろう
- ・ ろくでなしの意味と語源とは
- ・ 夜空に輝く星は何個まで見ることが出来るのか?
- ・ 「いつから通貨を円と呼ぶようになった?」日本円の名前の由来
- ・ 出前寿司にアカガイ(赤貝)が入らない理由
大文字焼きはなぜ「大」の字なのか?
最終更新日:2020/10/21

画像引用元:wikipedia「五山送り火」
京都の夏の風物詩として知られる「大文字焼き」ですが
京都を囲む5つの山の1つ、
「如意ヶ岳(にょいがだけ)」の中腹に描かれている「大文字」はなぜ大文字なのでしょうか?
なぜ大文字?

画像引用元:wikipedia:「五山送り火」
「大」の文字が書きだされる理由は諸説あり、次のような理由が挙げられています。
・「大」の字の端を結ぶと五芒星になるため、古くから魔除けとして使われた説。
・神の化身と考えられた北極星をかたどったものが「大」になった説。
・弘法大師(こうぼうだいし)空海が大の字型の護摩壇を(ごまだん)を組んだことから来た説。
全国的にも有名な行事ですが、なぜ大文字でいつ始まったのかは
史料ごとに様々な説があるため、かなり不明確で意外にもわかっていないのです。
そもそも大文字焼きというのは・・・

画像引用元:wikipedia:「大文字焼き」
大文字焼きではなく「五山の送り火」、「大文字送り火」が正しい呼び方。
京都において「大文字焼き」と呼ぶのは間違いで
現在の公式な呼び方は「五山送り火」や「大文字送り火」と呼ぶようです。
しかし、江戸時代までは「大文字焼き」と呼ばれていたという記録が残っており
「五山の送り火」と呼ばれるように変化したのは、戦後もしくは昭和以降とされています。
そして、現在の京都出身者でも「大文字焼き」と呼ぶ人もいるので
「大文字焼き」もしくは「大文字送り火」「五山の送り火」と覚えておきましょう。
--
以上、大文字焼きはなぜ「大」の字なのか?でした。
他の地域・社会の雑学
他の雑学(ランダム表示)
--