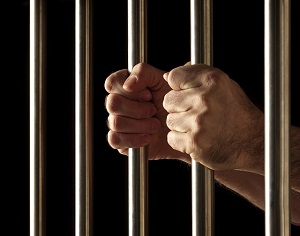- ・ 2席分必要な大柄の乗客が飛行機に乗ると料金はどうなる?
- ・ 「じゃがりこ」の名前の由来とは
- ・ 電柱は1本いくらするのか?その値段とは
- ・ 初雪?終雪?夏に雪が降った場合の呼び方
- ・ おいそれの意味と語源とは
- ・ やにわにの意味と語源とは
- ・ 川の水が流れ込んでも海水が薄くならない理由
- ・ 世界一危険な鳥!?「ヒクイドリ」ってどんな鳥?逃げる方法は?
- ・ シャンメリーはなぜクリスマスの定番になったのか?
- ・ 日本の電車のリクライニングシートはアメリカ人のわがままで生まれた
- ・ 世界一短いエスカレーターが日本にある
- ・ 新人のことを表す「新米」の語源とは?
- ・ 髭は朝に多く伸びるので出かける寸前に剃ろう
- ・ 冷蔵庫のコンセントが高い位置にある理由
「いつから通貨を円と呼ぶようになった?」日本円の名前の由来
最終更新日:2020/10/21

そういえば、日本はいつから「円」になった?
「越後屋そちも悪よのう」 「いやいや、お代官様ほどでは」と言うやり取りから
小判を渡す有名なやり取りがありますが、ここでの小判の呼び名は「両」(りょう)と言います。
江戸時代では両(りょう)分(ぶ)朱(しゅ)をはじめとする金貨・銀貨が使われていました。
ではいつから日本は円と呼ぶようになったのか。
円の名前の由来
実は円の名前の由来は明確になっていません。
諸説ありますが有力なのは次の3つ
1、18世紀ごろ、メキシコドル(洋銀)がヨーロッパ諸国、中国やアジア諸国に大量に流入しており、
中国ではその形から「銀円」「洋円」と呼ばれていたので、日本も真似て「円」と呼ぶようになった。
2、明治時代初期、財務担当参議だった大隈重信が、
衆議で「みんな指で輪を作りお金を表している」と主張し「円」になった。
3、明治時代初期の幣制改革の際、
硬貨を方形から円形に統一されたため、その形から「円」と呼ぶようになった。
個人的には1が有力だと思います。
明治時代の日本は他国の文明・文化を学習し、
吸収していたのでその影響から様々な過程を経て円となったのではないだろうか。
まとめると
円は明治時代から呼ばれるようになり使われ始めた。
と言うのが結論です。
明治4年5月10日に新貨条例が制定され、日本の貨幣単位として円が正式に採用されているので
wikipediaの新貨条例を一度読むことでより詳しく理解できると思います。
1円以下の通貨も存在していた
実は1円以下の補助単位と通貨がありました。
1銭(せん):1円の100分の1(1円=100銭)
1厘(りん):1円の1000分の1 1銭の10分の1(1円=1000厘)(1銭=10厘)
1銭、1厘の硬貨や紙幣も昔は流通していましたが、
法律により小額通貨が整理されることになり、
1953年12月31日を最後に1円未満の通貨の使用、
流通が禁止され、今現在も流通していません。
ただし「銭」に関しては、
ニュース等で為替や株式で〇円〇銭と表示されるので見たことある方も多いはず。
~
ちなみに、五円玉の周りに書かれているギザギザが何か知っていますか?
・五円玉の穴の周りにあるギザギザは何を表している?
--
以上、「いつから円と呼ぶようになった?」日本円の名前の由来でした。
<関連>投資(株・FX)まとめサイト速報!
--