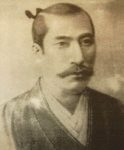- ・ 間食のことを「おやつ」と呼ぶ理由
- ・ てんてこ舞いとはどんな踊り?
- ・ イカの足は10本ではない!?足と呼ばれる部分の名前とは
- ・ ククレカレーの「ククレ」の名前の由来・意味とは
- ・ 男はなぜ禿げるのか?原因と育毛剤の話し
- ・ アイシャドーの元々の目的とは?
- ・ 嘘ではない。なぜ4月1日は早生まれなのか?
- ・ 数の子の名前の由来・語源とは?
- ・ サウジアラビアやドバイが砂を輸入している理由
- ・ するめのことを「あたりめ」と呼ぶ理由
- ・ ごぼうを食べるのはごく一部の国だけ!?日本が食べるようになったのは
- ・ 体重計に乗るだけで体脂肪を測定できる仕組み・原理は?正確な測定方法は?
- ・ 普通免許があれば消防車を運転できる!?
- ・ カタツムリはコンクリートでカルシウム補給している
武士の給料はなぜ米だったのか?その理由
最終更新日:2020/10/21
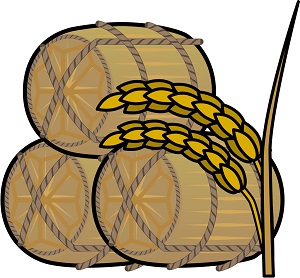
現代の日本では、一般的なサラリーマンが貰う給料は「お金」です。
ですが、昔の日本はその給料を「米」で支払われていました。
なぜ、武士の給料は「米」だったのでしょうか?
なぜ米が武士の給料?

領地を主君から与えられていたから。
武士が主君に仕えて、そのお礼(給料)として貰っていたお米。
これは「領地を主君から与えられていたから」という考えから、
領地で納められていた税が、自分の収入になっていました。
収められていた税と言えば・・・

農民から税として納められていたのが「米」。
当時の税と言えば、知っての通り「米」です。
そして、武士が主君から貰うのは「領地」であり「石高」と呼ばれるもの。
石高とは『米の収穫量』だったため、
その領地で収穫できる米を武士に与える、これが昔の「給料」のようなものでした。
「給料=米」だったのか?

現金や味噌が配られる事もあった。
しかし、全部を米で支給されていたという事はなく、
米と現金の両方で支給したり、味噌や炭なども支給することもありました。
なので、現金がまったく支払われなかったというわけではなかったようです。
石高と呼ばれるまでの道のり
戦国時代前期までは、税がお金だった。
鎌倉~戦国時代前期では平均米の収穫量を通貨に換算し「貫」を単位として表された「貫高制」でした。
これは納めるべき米をお金(銭)で代わりに収めるというものでした。
ですが、当時の日本は貨幣を自給できなかった事や、貨幣の質が悪い「鐚銭(びたせん)」の問題もあったため
貫高制の普及に伴い、それを維持する十分な貨幣流通量が確保できなくなっていました。
戦国時代後期になると、これらの問題から米などが代わりに収められるようになっていきました。
そして、安土桃山時代では「豊臣秀吉」の太閤検地によって、武士に支給される単位が「石高」で表されるようになり、
税を米で納める「石高制」が生まれ、江戸時代でも貨幣の製造が行われていたが、石高制が維持されていたようです。
~
米と言えば、新人を指す「新米」の語源が何か知っていますか?
・新人のことを表す「新米」の語源とは?
--
以上、武士の給料はなぜ米だったのか?その理由でした。
--