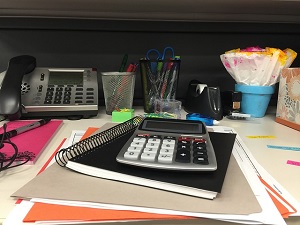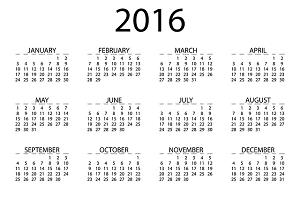- ・ 鮭が生まれた川に戻って来られる理由
- ・ 開店祝いで置かれている花はいくらする?その値段や名前とは
- ・ チキン・ナゲットの「ナゲット」の意味とは
- ・ キウイフルーツの正しい食べ方は皮ごと食べる!?
- ・ なぜ月は追いかけてくるように見えるのか?
- ・ 冷蔵庫のコンセントが高い位置にある理由
- ・ モヤシを育てていくとどうなるのか?
- ・ 鯱張るの意味と語源とは
- ・ てるてる坊主はもともと「娘」のことだった
- ・ 月の昼と夜の温度ってどのくらいなのか?
- ・ ハートの形をしたクローバーはクローバーではない!?その理由
- ・ 「若さってなんだ?」と子供に聞かれたら答えたいこと
- ・ 犬と猫はどちらが強いのか?vsダックスフントの場合
- ・ イチかバチかの意味と語源とは
漢方薬には湯のつく文字が多いのはなぜ?
最終更新日:2020/10/21

漢方には「桂枝湯(けいしとう)」や「麻黄湯(まおうとう)」など
湯のつく文字が多いですがなぜでしょうか?
湯がつく文字が多い理由

薬を湯で溶かして飲むことから最後に湯がついている。
現代では漢方は液状のもので売られているものも多いが
元々は生薬としてお湯で溶かしてから飲むものが一般的でした。
生薬(しょうやく)とは、東洋医学の歴史と経験論から鉱物だったり植物を
そのまま利用したり加工したりなどして飲まれます。
生薬に関してはこちらを見ましょう。⇒回生薬局「生薬とは」
湯とはどのぐらいの温度なのか?

湯は熱すぎず冷たすぎない温かい温度のことを言う。
漢方の考え方は陰と陽の関係で考えられることが多く、陰だと冷たすぎで陽は熱すぎます。
陰陽をバランスよく調和した状態が「温」なのです。
つまり、熱すぎず、冷たすぎない温度で薬を飲むことが体にとって良い事なので
ほどよい温度で漢方を飲むことが正しい飲み方だとされ、「ほどよい温度=湯」となるのです。
--
以上、漢方薬には湯のつく文字が多いのはなぜ?
他の薬の雑学
他の雑学(ランダム表示)
--