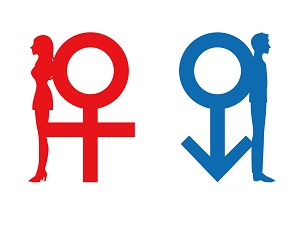- ・ カラスの鳴き声が不吉と言われる理由と、夜に鳴く意味とは?
- ・ ハリウッドが映画の聖地になった理由
- ・ 誰でも弾ける!?「史上最も静かな曲」
- ・ 急須の蓋の穴はなぜ付いている?その理由とは
- ・ 「なんで自分ばかり…」と思う癖を無くすコツ
- ・ 夕方や夜に新しい靴をおろしてはいけない理由
- ・ アメリカはなぜ「合州国」ではなく「合衆国」という漢字なのか?
- ・ 「赤とんぼ」という名前は正式名称ではない
- ・ ちりめんじゃこの魚の種類と語源・由来
- ・ なぜ青や緑?手術着の色が白ではない理由とは?
- ・ オツな味の「オツ」の意味と語源とは
- ・ 回転寿司で食べられる大トロはメタボのマグロ!?
- ・ ダイヤモンドを評価する「4C」とは何のこと?その意味とは
- ・ 書類送検の書類とは何の書類で、どんな意味なのか?
手塩にかけるの「手塩」とは何のこと?
最終更新日:2020/10/21

「手塩にかけた弟子」「手塩にかけた部下」など
自ら面倒を見て育てることを意味する言葉なのだが
この「手塩」とはいったい何のことなのだろうか。
「手塩」の語が見られるようになった室町時代

※wikipedia「塩」より引用
昔、食事をするときはそれぞれ自分のお膳で食べていたのですが
そのお膳には塩が添えられていました。
この塩を各自好みに応じて食べ物に加えていたそうです。
この塩の膳は元々不浄を払うために使うものでした。
その塩の名称を「手塩」と言いました。
手塩は他人ではなく自分でかけるもの。
「自らの手でかけることで加減を調節する」ことから
「自ら世話をする」という意味を持ち「手塩にかける」という言い方ができたとされています。
「手塩にかける」という言葉が使われ始めたのは江戸時代ごろからとされています。
--
以上、手塩にかけるの「手塩」とは何のこと?でした。
他の言葉・漢字の雑学
他の雑学(ランダム表示)
--