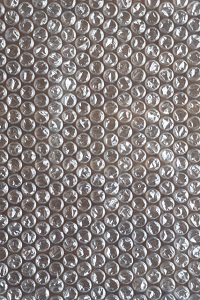- ・ 飛行機のタイヤに窒素を入れる理由とは?空気との違いは?
- ・ トライアスロンが誕生した理由とは
- ・ 高級ブランド「ブルガリ(BVLGARI)」はなぜBULGARIではないのか?その理由
- ・ 「にっちもさっちもいかない」とはどういう意味?その由来
- ・ ゴミ収集車1台の値段っていくら?
- ・ 湯たんぽの表面がデコボコになっている理由とは
- ・ 店の前に置かれているタヌキの置物は何?その意味とは
- ・ うどんはいつから食べられるようになった?その歴史
- ・ 目から鱗が落ちるの意味と語源とは
- ・ 流行色はどうやって決まっているのか?
- ・ 牛が草だけ食べて大きくなる理由
- ・ 一富士二鷹三茄子には続きがある
- ・ 初めてSOS信号が使われた船はタイタニック号ではない
- ・ もみじ饅頭の誕生には有名な政治家が関わっていた!?
鯖寿司が京都名物になっている理由
最終更新日:2020/10/21

鯖寿司(サバずし)は京都名物の一つになっていますが
なぜ、内陸の都市である京都に海の魚が名物料理となっているのでしょうか?
画像引用元:wikipedia「鯖寿司」
鯖寿司が名物料理の理由

画像引用元:wiipedia「サバ」
腐敗防止のため塩をふったことがきっかけ。
昔、日本海で獲れた魚は人の手によって京都まで運ばれていました。
しかし、運ぶのには丸一日かかっていたので、サバは腐ってしまいます。
なので、水揚げされたサバを腐敗防止のために塩がふられ
京都へ運ぶと、その塩がちょうどよい味加減となり、美味しくなっていました。
その塩サバから発展して、サバ寿司が生まれたのです。
サバが運ばれてきた道

画像引用元:wikipedia「鯖街道」」
サバが運ばれていた街道を「鯖街道」と呼ぶ。
京都の上の若狭国(わかさのくに)など
京都までを結ぶ街道の総称を「鯖街道」と呼ばれていたようです。
主に魚介類を運搬していたルートでしたが、サバが最も多かったことから
このような名前が付けられています。
--
以上、鯖寿司が京都名物になっている理由でした。
他の食べ物の雑学
他の雑学(ランダム表示)
--