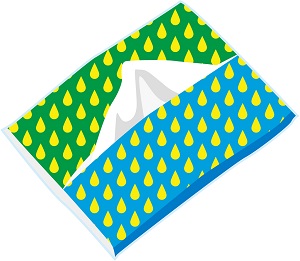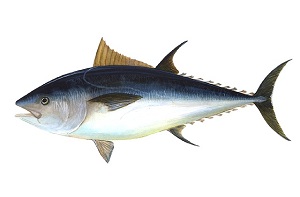- ・ 足元を見るの意味と語源とは
- ・ 人脈づくりで注意するべき事とは?
- ・ 腐っていないのに豆腐と呼ばれている理由
- ・ 雷は空から落ちるだけではない?
- ・ リュックサックに付いている「ブタ鼻」の意味とは?
- ・ <陸上競技>トラックのレーンの並び順はどうやって決める?
- ・ 宅配クリーニングの利用増に伴い苦情が増加。注意点を知ろう。
- ・ 道路標識はいくらする?その値段とは
- ・ 網戸から蚊が入る理由とは?
- ・ 意外と知られていないクラーク博士のその後
- ・ なぜ犬の定番の名前が「ポチ」なのか?その由来とは
- ・ 普通の金庫だと火事で中身が燃える理由
- ・ ルビーとサファイヤは同じ!?その違いとは
- ・ ピロリ菌を除菌しても胃がんになる可能性はある!?その理由
つつがなくの意味と語源とは
最終更新日:2020/10/21

「つつがなくおこなわれた」
このような感じで使われる言葉ですが
では、「つつがなく」とはどういう意味なのでしょうか?
つつがなくの意味とは?

支障がない事や無事な事を意味する。
「今日の式典はつつがなく行われた」や
「つつがなくお過ごしでしょうか?」など相手の安否を尋ねると気にも使われている言葉です。
つつがなくの語源は?

病気や災難などの心身が痛むようなことや差し障りが「つつが」と言われている。
つつがなくの「なく」は「なし・ない」という意味なので「つつが」と「なし」に分かれます。
一説には「つつが」とは「痛処(つつが)」や「障(つつみ)」つまり、病気や災難などの心身が痛むようなことや
差し障りを「つつが」と言われているようです。
そして、「心身が痛むようなことがない」という無事で
支障のない事から「つつがない」となったのではないかとされています。
常に否定形で用いられていますが、平安時代ごろには悩み事などの障りがあることを「つつがあり」ということもあったようです。
また、かつて東北地方で発生した「恙病(つつが)」またはこの病気を媒介とする「恙虫(つつがむし)」に由来するという説もあります。
つつがなくの類語
・変わりなく
・お元気で
・健康で etc.
つつがなくの類語で、よく知っている言葉は
このようになっています。
~
関連で、めどがつくの語源が何か知っていますか?
・めどがつくの意味と語源とは
--
以上、つつがなくの意味と語源とはでした。
他の言葉・漢字の雑学
他の雑学(ランダム表示)
--