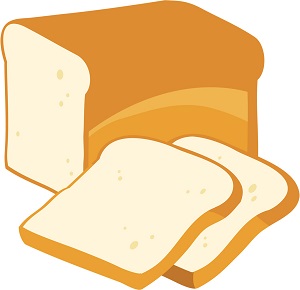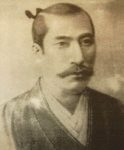- ・ 缶の緑茶飲料を開けると炭酸飲料みたいに音が出る理由
- ・ モンドセレクション受賞=美味いなのか?
- ・ 一姫二太郎の本当の意味
- ・ 用心棒の意味や語源とは
- ・ 「若さってなんだ?」と子供に聞かれたら答えたいこと
- ・ 相手が打った数字がわかる電卓を使った数字マジック
- ・ 毒を持つ鳥が存在する!?持っている毒の種類とは
- ・ カレンダーに記されている六曜の意味とは
- ・ お札の肖像画は誰が書いているのか?
- ・ パソコンのマウスが動く距離の単位はあの人気キャラクターが関係している!?
- ・ 「とどのつまり」の「とど」の由来とは
- ・ ずぼらの意味と語源とは
- ・ マグロが泳ぐのをやめると死ぬ理由
- ・ 海老と蝦の違いとは?
鯖寿司が京都名物になっている理由
最終更新日:2020/10/21

鯖寿司(サバずし)は京都名物の一つになっていますが
なぜ、内陸の都市である京都に海の魚が名物料理となっているのでしょうか?
画像引用元:wikipedia「鯖寿司」
鯖寿司が名物料理の理由

画像引用元:wiipedia「サバ」
腐敗防止のため塩をふったことがきっかけ。
昔、日本海で獲れた魚は人の手によって京都まで運ばれていました。
しかし、運ぶのには丸一日かかっていたので、サバは腐ってしまいます。
なので、水揚げされたサバを腐敗防止のために塩がふられ
京都へ運ぶと、その塩がちょうどよい味加減となり、美味しくなっていました。
その塩サバから発展して、サバ寿司が生まれたのです。
サバが運ばれてきた道

画像引用元:wikipedia「鯖街道」」
サバが運ばれていた街道を「鯖街道」と呼ぶ。
京都の上の若狭国(わかさのくに)など
京都までを結ぶ街道の総称を「鯖街道」と呼ばれていたようです。
主に魚介類を運搬していたルートでしたが、サバが最も多かったことから
このような名前が付けられています。
--
以上、鯖寿司が京都名物になっている理由でした。
他の食べ物の雑学
他の雑学(ランダム表示)
--