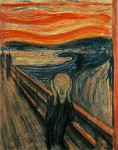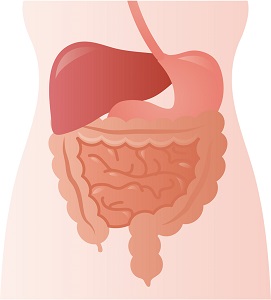- ・ けんもほろろの意味や語源とは
- ・ ソフトボールのボールはなぜ大きい?理由が意外!
- ・ 切り干し大根の開封後の保存期間と保存方法
- ・ 日本の神様の名前に「みこと」が付く理由
- ・ 本物もある!弁当に入っている緑のギザギザの名前とは?
- ・ 初夢は本来、正月に見た夢のことではなかった
- ・ 「若さってなんだ?」と子供に聞かれたら答えたいこと
- ・ なぜ風呂に敷いてないのに風呂敷と呼ぶ?その名前の理由とは
- ・ チーズを撃って勝った海戦がある!?
- ・ クジラが陸上で生きられない(すぐ死ぬ)理由
- ・ 楽天のポイント10倍の大きな罠に気を付けろ!
- ・ 関の山の意味と語源とは
- ・ なぜ時間が経つとレシートの文字は消えるのか?
- ・ 水族館でスルメイカを見かけない理由
箔がつくの「はく」とは何のこと?その由来
最終更新日:2020/10/21

「箔がつく」という言葉があります。
意味は値打ちが高くなることや人物に貫禄がつく際に使われます。
では、この箔(はく)とは何のことなのでしょう?
箔(はく)とは?

画像引用元:wikipedia「金箔」
箔がつくとは金箔や銀箔のはくのこと。
箔の由来は蒔絵(まきえ)や襖絵(ふすま)などを付ける金箔や銀箔から由来しているとされています。
金や銀を金槌で叩いて薄くのばすことで箔にしたもののことを言いい、この箔はとても薄く、剥がれやすい特徴を持っています。
※蒔絵とは漆工芸技法の一つで、漆器に金や銀の金属粉をまいて器につける技法のこと。
剥がれやすいがゆえに・・・

画像引用元:wikipedia「金箔」
剥がれやすいため、人間の地位や肩書を失った時に使われることも。
箔がつくの反対に「箔が落ちる」という言葉があります。
どんなに高価な工芸品でも、箔が剥がれてしまうとその価値は一気に下がることから、
人間の場合でも地位や肩書を失うと本性が見えてくるときなどで使われることもあります。
--
以上、箔がつくの「はく」とは何のこと?その由来でした。
他の言葉・漢字の雑学
他の雑学(ランダム表示)
--