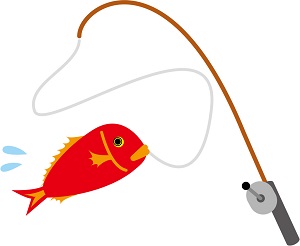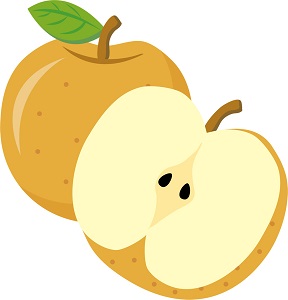- ・ 九十九里浜は99里なのか?その語源と実際の長さ
- ・ 夏休みはなぜ長い?その理由と由来
- ・ ポテトチップス1袋にはジャガイモが何個入っているのか?
- ・ しのぎを削るの意味と語源とは
- ・ チーズを切るナイフが波型になっている理由とは
- ・ なしのつぶての意味や語源とは
- ・ オツな味の「オツ」の意味と語源とは
- ・ ニジマスはもともと日本にはいなかった!?
- ・ きっかけが凄い!サッカーのスローインはなぜ両手で投げる?
- ・ モグラは小食ではなく大食い?!その理由とは
- ・ ホワイトハウスの名前の由来とは
- ・ 脱皮は爬虫類や昆虫だけじゃない!脱皮するイルカがいる
- ・ なぜ月は追いかけてくるように見えるのか?
- ・ テンパるの意味と語源とは
床の間と呼ばれる理由とは
最終更新日:2020/10/21

画像引用元:http://yoshihei.052e.com
床の間とは日本住宅の畳がある部屋の座敷飾りの一つと言われています。
では、この床の間が呼ばれる理由とは何なのでしょうか?
床の間と呼ばれる理由

画像引用元:wikipedia「床の間」
畳より一段高い床を作ったことから床の間と呼ばれるようになった。
昔の日本屋敷は板張りの床で、畳は寝具として使われていました。
室町時代になると、その畳が家中に敷き詰められる日本屋敷「書院造(しょいんづくり)」の住宅の様式になると
畳の床よりもさらに一段高い床が作られ「床の間」と呼ばれるようになったのです。
また、床の間とは俗称で正しくは「床(とこ)」と呼びます。
床の間には何をする場所?

画像引用元:wikipedia「床の間」
美術的に価値の高い絵や置物を置いて鑑賞するもの。
床の間は昔、神を祀る(まつる)場所とされており、神や仏を書いた絵や教えを書いた掛け軸を飾ったり
灯火ともしてお供え物を供えるなどするところでした。
これが転じて美術的に価値の高い絵や置物を置いて鑑賞するようになったのです。
また、茶道のマナーの一つに床の間の掛け軸や花などの鑑賞をするといったことにも床の間は使われています。
--
以上、床の間と呼ばれる理由とはでした。
他の地域・社会の雑学
他の雑学(ランダム表示)
--