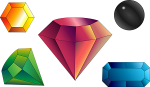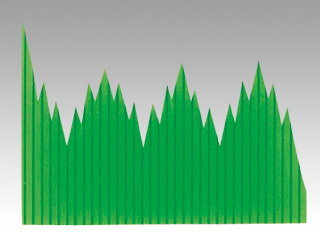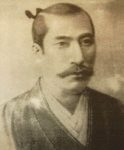- ・ 名刺はなぜ名紙ではないの?その由来とは
- ・ 盲導犬の指示(命令)はなぜ英語なのか?
- ・ 逆立ちで食べても逆流しない?人間の体の仕組みとは?
- ・ ガソリンメーターの横にある三角マークの意味とは
- ・ 豆板醤の原料となる「豆」は大豆ではない!?
- ・ なぜガソリンスタンドの屋根は高いのか?
- ・ 栄養ドリンクが茶色い瓶に入っている理由とは
- ・ おやつ代も?!選挙スタッフに支払うお金が決められているその理由
- ・ なぜ?プードルを独特のカットにする意味とは?
- ・ タコのスミは目くらましのためだけではない?
- ・ マーガリンやドレッシングが出るあの容器の名前とは?
- ・ 日本に犬を飼えない島がある
- ・ なぜ高い所から見下ろすと足がすくむのか?その理由
- ・ プリマハムの「プリマ」とはどういう意味なのか?
戦国時代の武将は今のような馬には乗っていなかった!?
最終更新日:2020/10/21

現代の一般的な馬とは、競馬で出てくるような馬のことを指していることでしょう。
では、日本の昔の戦国時代の馬は、今のような馬ではなかったというのは知っていますか?
戦国時代の馬とは?

現在のポニーぐらいの大きさの小さな馬だった。
現代の馬は、競馬場で走っているような馬を一般的には指していますが、
戦国時代の馬は、ポニーと呼ばれるような小さな馬だったのです。
ポニーは、肩までの高さが147cm以下の馬のことを言います。
なぜ、ポニーぐらいの馬?

戦国時代の武将は身長が低かった。
戦国時代の有名な武将で例を挙げると、
・織田信長:170cm
・徳川家康:159cm
・豊臣秀吉:140cm
と、長身と言われていた織田信長でも170cmほどでした。
また、当時の成人男性の平均身長は159cmと低かったのです。
ポニーの大きさだと、走る速度もあまり速くないですが、
それでも人を乗せた状態で100mを走らせると、時速40kmぐらいの速さだったようで
当時の武将の身長的には、戦や移動においては活躍できたのではないかとされています。
ちなみに

今のような馬が登場したのは18世紀初め。
競馬などで走っている馬が登場したのは、18世紀初め頃で
イギリスでアラブ馬や狩猟に用いられていた品種などから
品種改良して生まれたのが、サラブレッドと呼ばれる軽種馬です。
~
競馬と言えば、競馬のメインレースは一番最後でない理由は知っていますか?
・競馬のメインレースを最終レースにしない理由
--
以上、戦国時代の武将は今のような馬には乗っていなかった!?でした。
他の歴史の雑学
他の雑学(ランダム表示)
--