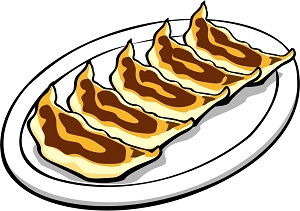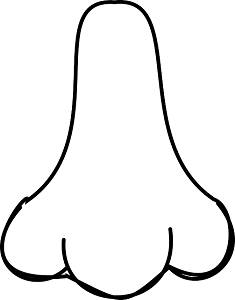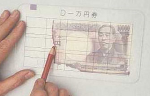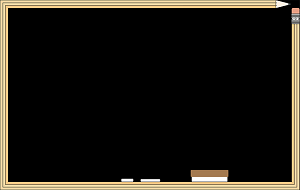- ・ 市場に並ぶマグロのドレスやマルとは何のこと?
- ・ 幽霊に足がないイメージが強い理由とは
- ・ 日本で最初に天ぷらを食べた偉人とは
- ・ 「ウコンを飲んだから二日酔い対策はバッチリ!」と思うのは間違い!?
- ・ 銀行の業界用語「だいてください」とは?
- ・ 日本で割り勘を考えた人物とは
- ・ 家にいるクモはほぼ巣を作らない
- ・ なしのつぶての意味や語源とは
- ・ 電柱は1本いくらするのか?その値段とは
- ・ 卵を割らずに鮮度がわかる方法とは
- ・ 回転寿司のコンベアっていくらするの?その値段とは
- ・ なぜトンボは逆立ちをするのか?←凄い効果がある
- ・ 2016年、転職サービスはヘッドハンティング型がさらに人気に
- ・ シジミやウコン以外の二日酔いに効果のある方法(食べ物)とは?
漢方薬には湯のつく文字が多いのはなぜ?
最終更新日:2020/10/21

漢方には「桂枝湯(けいしとう)」や「麻黄湯(まおうとう)」など
湯のつく文字が多いですがなぜでしょうか?
湯がつく文字が多い理由

薬を湯で溶かして飲むことから最後に湯がついている。
現代では漢方は液状のもので売られているものも多いが
元々は生薬としてお湯で溶かしてから飲むものが一般的でした。
生薬(しょうやく)とは、東洋医学の歴史と経験論から鉱物だったり植物を
そのまま利用したり加工したりなどして飲まれます。
生薬に関してはこちらを見ましょう。⇒回生薬局「生薬とは」
湯とはどのぐらいの温度なのか?

湯は熱すぎず冷たすぎない温かい温度のことを言う。
漢方の考え方は陰と陽の関係で考えられることが多く、陰だと冷たすぎで陽は熱すぎます。
陰陽をバランスよく調和した状態が「温」なのです。
つまり、熱すぎず、冷たすぎない温度で薬を飲むことが体にとって良い事なので
ほどよい温度で漢方を飲むことが正しい飲み方だとされ、「ほどよい温度=湯」となるのです。
--
以上、漢方薬には湯のつく文字が多いのはなぜ?
他の薬の雑学
他の雑学(ランダム表示)
--