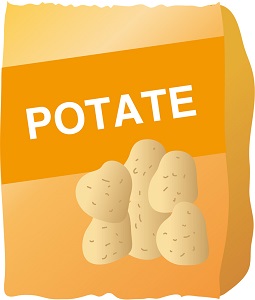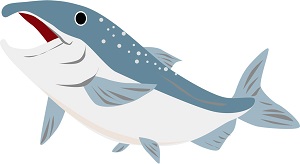- ・ お寺が日本一多い都道府県はどこ?
- ・ 業務用シーチキンの種類一覧と解説
- ・ お開きの意味と語源とは
- ・ 逆立ちで食べても逆流しない?人間の体の仕組みとは?
- ・ ローズマリーの保存期間と保存方法
- ・ 千手観音の手が千本も無いのになぜ千手なのか?
- ・ 2016年に手作りクリスマスケーキが増えた理由(多分)
- ・ 妖怪と幽霊、お化けの違いとは
- ・ Bluetooth(ブルートゥース)の名前の由来って何?
- ・ 駅の番線はどういう基準で決められているのか?
- ・ 岐阜の方言「キモい」の意味とは?
- ・ 緊急電話番号が119や110の理由とは?
- ・ オシドリの夫婦は仲があまり良くない!?
- ・ 北海道の方言「こわい」の意味とは?
塩豆の周りについている「白い」のは何?
最終更新日:2020/10/21

塩豆には、豆の周りに白くコーティングされたようなものがあります。
一体、あれは何なのでしょうか?
画像引用元:http://item.rakuten.co.jp/mamefuku/
白い粉の正体とは?

画像引用元:wikipedia「カキ(貝)」
あれは牡蠣の殻。
あの白い粉の正体は、牡蠣の殻の粉で「胡粉(ごふん)」と呼ばれるものです。
実はあの白いコーティングは牡蠣によるものだったのです。
どのように作っている?

画像引用元:http://ajihonpo.jp/SHOP/ss001.html
まず牡蠣は、からの大きい「イタボガキ」が使われているそうです。
過程は次のようになっています。
1、殻を長期間天日干しする。
2、石臼(いしうす)で殻をこすり合わせて汚れを取る。
3、粉を水の中に入れて上澄み(うわずみ)だけを取る。
この作業を何度も繰り返して、「胡粉」が出来上がります。
そして、水洗いして3日ほど寝かせたエンドウ豆を網の上で煎り
そこに胡粉や塩水を混ぜた液体などをふりかけることで、白い塩豆が出来上がるのです。
--
以上、塩豆の周りについている「白い」のは何?でした。
他の食べ物の雑学
他の雑学(ランダム表示)
--