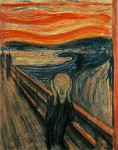- ・ ヘッドハンターはどこから人材情報を得ているのか?
- ・ 食卓のナイフの刃先が丸い理由とは
- ・ コーヒー豆の種類による味の違いを知る一番良い方法
- ・ 飛行機で宇宙までいけない理由
- ・ 新品の靴下を束ねている金具の名前とは
- ・ 安物スーツケースでは相手にされない?贅沢旅には高級品を
- ・ 牡蠣(カキ)がホタテの貝殻で養殖される理由とは?
- ・ サラリーマンとビジネスマンの違いとは?
- ・ ギリシャの国歌は158節もあるので2節しか歌わない
- ・ 睡眠時間が最も長い・短い動物は何?
- ・ 死んでからも髭が伸びるように見える理由
- ・ ハードル走の雑学!なぜ男性は110mで女性は100m?歴史は?
- ・ 雑貨店や小さな店のレジが奥にある理由
- ・ キャビアが高級食材の理由とは
中世ヨーロッパでは動物裁判が行われていた
最終更新日:2020/10/21

裁判と聞くと、原告となるのは人間ですが
中世ヨーロッパでは原告が動物となる「動物裁判」が広く行われていたことがあります。
動物裁判とは?

画像引用元:wikipedia「日本の裁判所」
人間に危害を加えた動物が裁かれる裁判。
13~18世紀にかけてヨーロッパでは動物裁判が行われていました。
人間に危害を加えるなどした動物たちが法的責任を問うための裁判です。
有罪になった動物たちは、資料上確認できるだけで合計142件記録されています。
動物裁判が行われるのは、キリスト教世界において
罪を犯したものは人間、動物、植物、無機物であっても裁かれなくてはならないという文化によるものです。
もちろん、現代では成立しません。
どんな動物がどのように裁かれた?

動物裁判では、動物は次のような結果になっています。
・赤ちゃんを蹴り飛ばした豚⇒絞首刑。
・痒みで人を苦しめた南京虫⇒銃殺刑。
・農作物を荒らした害虫⇒破門宣告・強制退去。
※破門宣告とは、宗教の信徒をやめさせられるという事で、当時で言うところの死刑宣告に相当。
害虫は、ハエ、ミミズ、アリ、バッタ、モグラ、ネズミのことです。
もちろん裁判所から出頭するように言われましたが、もちろん来ることはないので
破門宣告や強制退去が言い渡されました。
弁護の甲斐があったネズミ
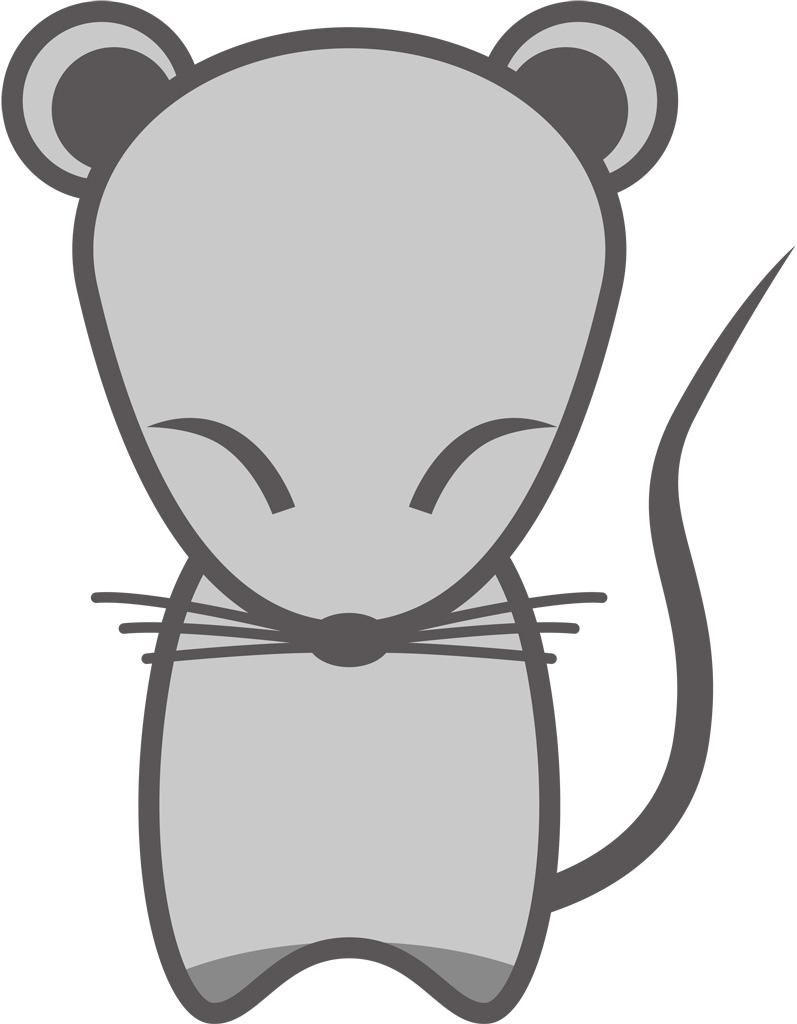
ネズミの立ち退きの際には川にネズミが渡るための橋がかけられた。
1519年には、イタリア北部の村でネズミが収穫物を荒らしたため裁判が行われました。
ネズミは村からの立ち退きを言い渡されましたが、ネズミ側の弁護人の弁護の甲斐があって
逃げていくときに、ネズミを傷つけない事と川にネズミが渡るための橋を架けるといった条件が認められた裁判もあったようです。
~
ねずみと言えば、実験でネズミだったり、モルモットが使われていますがなぜなのでしょうか?
・モルモットが実験動物になる理由とは
--
以上、中世ヨーロッパでは動物裁判が行われていたでした。
--