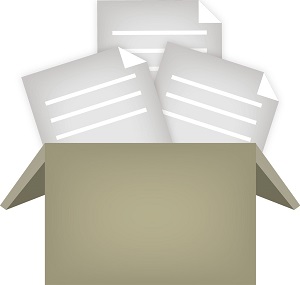- ・ べそをかくの意味と語源とは
- ・ 野球の投手と捕手をバッテリーと呼ぶのはなぜ?意味と語源
- ・ バス・電車のラッピング広告はいくらかかる?その値段とは
- ・ 水よりビールの方が大量に飲める理由とは?
- ・ 液晶テレビとプラズマテレビの違いを知ろう
- ・ ホテルや旅館の名簿に偽名で書くとどうなる?
- ・ 鯛は左目で値段が決まる!?その理由
- ・ 目白押しの意味と語源とは
- ・ 懐石料理と会席料理の違いとは
- ・ 船の名前にはなぜ××丸と名前を付けるのか?
- ・ チーズを撃って勝った海戦がある!?
- ・ 方言「やんばい」の意味とは?
- ・ 相撲の行司が短刀を持っているすごい理由とは?
- ・ 日本発のチェーン店は現在で言う100円ショップ。由来と歴史が面白い。
碁盤の足の形の意味や由来とは
最終更新日:2020/10/21

碁盤とは、囲碁で使われる板の事ですが、
この碁盤の足は変わった形をしていると思います。
この形をしている意味や由来とは何なのでしょうか?
碁盤の足の由来

画像引用元:wikipedia「クチナシ」
植物のクチナシから来ている。
クチナシの果実は熟しても割れないため、「口無し」という和名で呼ばれたりします。
碁盤の足の形は、植物の「クチナシ」の実の形を模したものなのです。
つまり、「打ち手は無言、周囲は口出ししてはいけない」という意味で付けられたようです。
口出しするとどうなるの?
首をはねられた。
口出し無用なのに、口をはさむと罰せられて
その首を、はねられていたようです。
ちなみに、碁盤の裏には四角いへこみのようなものがあります。
それは、「血だまり」と呼ばれており、首をはねた人の打ち首をその上に乗せて見せしめにしていたと言われています。
元々は「血だまり」と呼ばれていたようですが、一般的には「へそ」と呼ばれ、
その効果は、木材の乾燥による歪みや割れ防ぐためのものであったり、石を打ったときの音を響かせることが目的だったりします。
~
ちなみに、囲碁に使われる石は、大きさが違うというのは知っていますか?
・囲碁の石は大きさが微妙に違う理由とは
--
以上、碁盤の足の形の意味や由来とはでした。
他の物の雑学
他の雑学(ランダム表示)
--