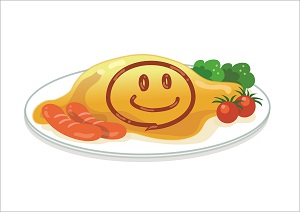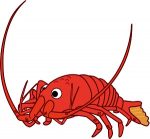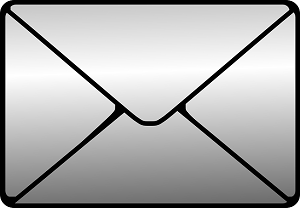- ・ 欧州で言われる「梯子の下を歩くと死ぬ」とは
- ・ 人脈を築くとき権力のある人ばかり見てはいけない!?その理由
- ・ ワインを横に寝かせて保存している理由とは
- ・ 打たない人でも知っておきたいパチスロの勝ち方の基本
- ・ 電話と電卓のボタン並びが違う理由
- ・ パセリの保存期間と保存方法
- ・ ニワトリに卵を産ませるのに電気代がかかる理由
- ・ 禁煙区域なのに「煙草する」!?その意味とは
- ・ ガソリンメーターの横にある三角マークの意味とは
- ・ 一番多いのはどこ?都道府県別「道の駅」数ランキング
- ・ 靴下の重ね履きは逆効果!?効果的な足元の温め方
- ・ 何もせずに仕事で大事な人と会ってはいけない理由
- ・ なぜ臆病者が「チキン」と呼ばれる?その理由
- ・ 白い喪服の意味
昔は電車から飛び降りる仕事の乗務員がいた
最終更新日:2020/10/21

電車から飛び降りる乗務員
そんなバカな!?と思ってしまいますが、
本当にそんな乗務員がいました。
なぜなのか?
日本発の電車

日本で初めて開業した電車は京都(1895年:明治28年)
街中を走る(路面電車)ため、危ないところは乗務員が電車から降りて、
電車の前を走り注意を促していました。
その乗務員は「前走り」と呼ばれていました。
蒸気機関車はあったものの、電車は結構な街中を静かに走るもの。
まだ慣れてなく整備も不十分なので、事故防止策をする必要があったのです。
当時、速度は約時速10km。
人間が走るよりもはるかに遅いスピードです。
だからこそ、飛び降りるという芸当ができました。
なお、乗務員ではありましたが、子供の役割だったようです。
体力がいるので子供に任せていたのでしょう。
ほぼアルバイトだと思います。
この仕事はいつ無くなった?
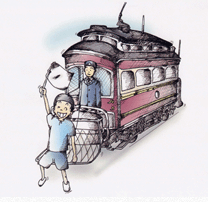
約10年後に無くなりました。
前走りが電車に轢かれることもあったようで、
これではいけないといろいろと対策をされて、
最終的には電車の前に「救助網」を設け、前走りを無くしました。
電車の前を人が走っていた。
なんとも昔らしい話しです。
ちなみに現在の路面電車は?

最高速度は例外を除いて40キロ。
ただ、ここまで速度を出せるところは少なく、
やはり渋滞する道路だと10キロ程度の速度になります。
車と違い、すぐに止まれないので、40キロでもかなり危険。
そして、現代は路面電車は道路を走るので、歩く人間に気を付けるのは交差点くらい。
信号さえ守れば轢かれる心配もほぼ無いので、救助網はありません。
路面電車はレールも簡易なものです。
線路を走る電車は石を敷いた専用のもの。
なぜ石を敷く?はこちら→線路に石を敷いている理由とは
--
以上、「昔は電車から飛び降りる仕事の乗務員がいた」でした。
他の乗り物の雑学
他の雑学(ランダム表示)
--